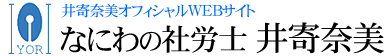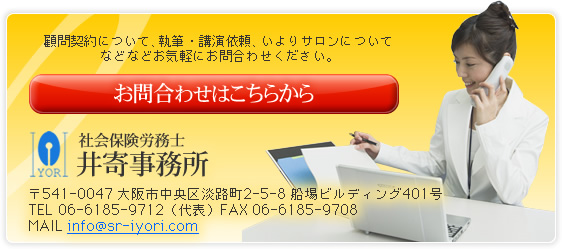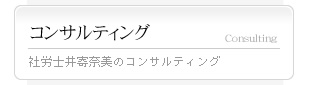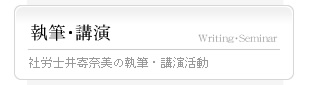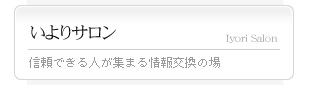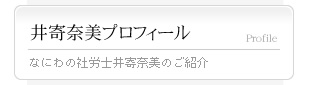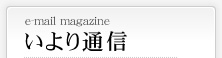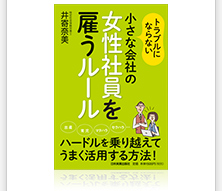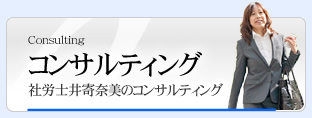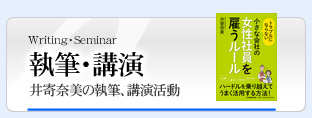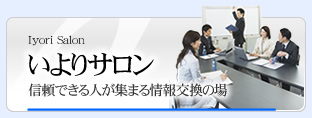いより通信:タイムリーな社会保険情報・助成金情報労務相談事例などを発信中!
叱咤激励のつもりがハラスメントに
みなさん、こんにちは。
社労士の井寄です。
11月に入り、一気に気温が下がりました。
大阪は、万博も終わり、万博会場への乗り換え駅となっていた
御堂筋線 本町駅の混雑が緩和されました。
お祭りが終わったあとの感じになっています。
それはさておき、先日、毎日新聞さんから取材を受けました。
新入社員の女性の方が、会社(従業員数50名くらい)の代表者から
叱咤激励を受けたあと、精神障害を発症し自死に至った事案に関し
このような重い結果に至ることを避けるために
指導側が気をつけるべきことといった内容についてお話させていただきました。
近年、精神障害の労災認定を求める労働者の数が増加しています。
厚生労働省では、毎年、請求件数、認定件数、認定に至った
強い心理的負荷を与えた業務上の出来事などを公表しています。
厚生労働省 令和6年度過労死等の労災補償状況
自分自身も経営者の立場ですので、部下への指導をどのように
行うか頭を悩ませることが多いです。
人は誰しも自分の価値観、自分の経験値で物事を考えてしまいがちです。
自分が、過去に受けた上司からの厳しい指導や、
顧客からの理不尽な要求などを乗り越えたからこそ
今の自分がある、とするポジティブ思考を持つ場合(←私もです)
部下のためにの「叱咤激励」が「ハラスメント」につながるケースも生じ得ます。
もちろん「指導」も「叱責」も上司の役割です。
しかし、その方法を令和流で行う必要があります。
昭和の過去の経験値は自分の中にしまいこみましょう。
「自分はこうしてきたから、それを他人に強要する」ことは
部下が自分の言うことを聞くことを前提とすることになります。
そのため、部下が言うことを聞かないと、
言うことを聞かないこと自体に対する叱責となってしまいます。
感情が高まり人格否定の発言などにもつながりやすいため注意が必要です。
上司がやるべきことは、部下の行動・判断により問題が生じた場合
まずはなぜその行動・判断をしたのか(しなかったのか)
部下の考えを聞くことです。
その上で、誰がやってもその問題は生じうるという観点で
(ターゲットを本人ではなく、「行動・判断」にあてる)
問題の再発をふせぐために、本人に防止策を考えてもらい
会社(上司側)ができるサポートを示すことが必要だと言えます。
そして、一般的に指導を行う立場の人が上になるほど
従業員は萎縮し、自分の考えが言えなくなる傾向があるため
誰が指導するのかの人選が重要です。
取材を受けたケースでは、社長自らの叱責でした。
社長からの叱責は、特に新入社員などにとっては
「最後通牒」と受け止められかねません。
叱責をする側の意識(叱咤激励)と
叱責された側の意識(会社に居場所がなくなる)が
異なることを上司側が強く意識する必要があると言えるでしょう。
11月給与の注意事項
1)年末調整の準備をすすめましょう。(年々複雑になっています)
国税庁 「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」
2)令和7年12月1日で健康保険証(プラスチックカード・紙)が廃止になります。
マイナ保険証への移行をしていない場合は、「資格確認書」で病院の受診をすることになります。
廃止に伴い、現在所持している健康保険証の回収・返却は不要です(各自が処分)
今月の気づき
とうとう博士論文が完成しました。
2016年4月に大阪大学法学研究科博士後期課程に入学し
10年目の奇跡です。
入学時点で3年で終わるとは考えていませんでしたが
まさか10年もかかるとは!
2025年は「論文ファースト」で、土日祝と平日19時以降は
ほぼ論文をやっていました。
毎月定例で参加している2つの勉強会のみなさんにも
12月まで休むと伝えて、まとまった時間の確保に努めました。
何度もくじけそうになりましたが、提出まであと少しです。
最終調整をして11月21日に提出し、
「おわったどーっ!」と空に向かって叫びたいと思います。
(万博の跡地だと人がいなくて広いのでよさそうです・笑)
長きにわたり見守り、はげましていただいたみなさま
ありがとうございました。
(2025年11月発行)