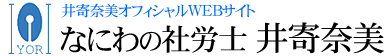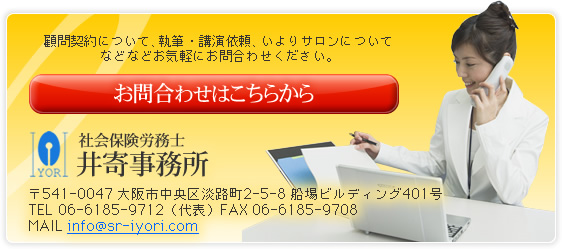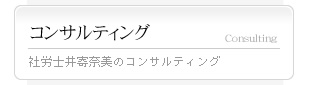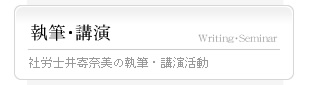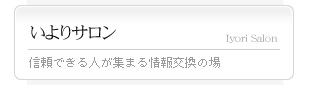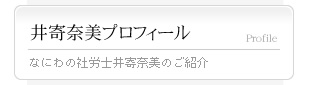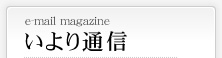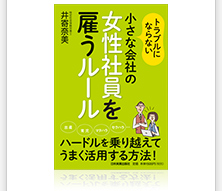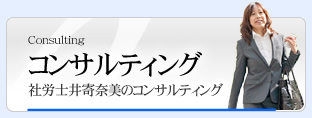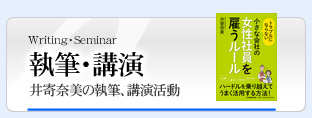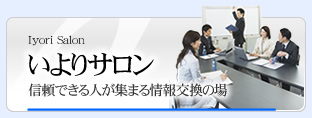いより通信:タイムリーな社会保険情報・助成金情報労務相談事例などを発信中!
2025年4月施行 雇用保険の新制度について
みなさん、こんにちは。
社労士の井寄です。
私が住む大阪は寒い日が続いたと思ったら
暖かい日がやってきたり、
また寒い日が続いたりしています。
私は、室内で仕事をしていますので
外気の影響は大きくないのですが
2月の連休前にめずらしく体調を崩してしまいました。
疲れをためるのがダメですね。
今思うと、その前から色々サインがありましたので
今後、サインを無視せず、早めに休むことを
心がけたいと思いました。
さて、年度末です。
今年の4月から始まる雇用保険の新制度がたくさんあります。
「雇用保険」じゃなく「育児保険」じゃないのか・・と
思わせるようなラインナップとなっております。
詳細はリンク先でご確認ください。
《育児に関する新給付》
①出生後休業支援給付の創設
*父母共に、一定期間内に育児休業を取得した場合に育児休業給付金が17%上乗せされる制度
(注意)双方が雇用保険の被保険者でない場合は、添付書類等必要。
⇒育児休業を取得する自社の労働者の配偶者の状況を確認する必要あり。
②育児時短就業給付の創設
*2歳までの子を養育する労働者が時短勤務制度を利用することで、賃金が下がった場合に
下がった賃金の最大10%を補填する制度
《定年後再雇用者に対する給付の引き下げ》
③高年齢雇用継続給付の支給率引き下げ
*令和7年4月1日以降に60歳到達者もしくは雇用保険加入5年を満たし受給権を得た
60歳以上65歳未満の労働者に対する高年齢雇用継続給付の支給率が引き下げになる。
(令和7年3月31日までに60歳到達もしくは、60歳到達後に受給権を得た労働者は旧来の制度適用)
《自己都合退職者の給付制限期間の短縮》
④自己都合で退職した労働者に対する失業給付受給までの待期期間が1ヶ月に短縮される。
(ただし5年以内に3回以上離職を繰り返している場合は3ヵ月)
上記の他
⑤育児休業給付金の期間延長手続きの見直し
⑥就業促進手当の見直し
会社の手続きとして直接影響があるのが①②③⑤かと思われます。
①(出生後休業支援給付)に至っては、これまでは会社その状況を
把握する必要がなかった、労働者の配偶者の状況を聞き出す必要が生じます。
おそらく制度は、「配偶者が入籍済みの会社員(雇用保険被保険者)」であることを前提としており
その場合は特に、配偶者の雇用保険番号を聞けばよいだけなので特に問題はありません。
しかし、そもそもシングルで出産など、上記前提と異なる場合、
例えば、配偶者と籍を入れられない関係であることなどについて
証明できる書類(←戸籍など)を自社の社員に準備してもらう必要が生じます。
かなりプライバシーの領域に踏み込まないと得られない給付となっています。
なぜ、こうなったのか。他の給付はすべて本人が休んでいるかどうかなど
本人の要件のみで支給決定できたものが、本給付は「配偶者も一定の期間に休んでいる」と
いう、本人以外の要件と紐づけしたことによって、このようになっています。
制度設計のときに、それに気づかなかったのか・・
いずれにせよ目標は「子どもを増やすこと」なので
配偶者云々を要件とせず、子どもを産んで育児休業を一定時期に取得した労働者
全員に上乗せすればよいのではないか・・などモヤモヤが残ります。
「上記前提と異なる場合」に添付すべき書類等は
厚生労働省 業務取扱要領(出生後休業支援給付)をご参照ください。
3月給与の注意事項
1)令和7年3月以降の健康保険料・介護保険料が変更になっています。
協会けんぽ 令和7年度 保険料額表
2)令和7年4月からの雇用保険料率(引き下げになります)
厚生労働省 令和7年度 雇用保険料率
今月の気づき
先日、長いおつきあいとなる同業者の友人と
これからの我々の業務のあり方について
話をしておりました。
給与計算業務ひとつについても
勤怠システムと連動型のもので
人の手をできるだけ介さずに処理が
できるようになっています。
(会社の計算ルールの正しい設定が前提)
相談業務についても、労使トラブルであれば、裁判例や該当条文
社会保険等の手続き関係であれば、そのフローや必要書類なども
検索で出てきます。
(どの情報が自社に適切なのかを見抜く力と、その手段をとった場合の
事後の影響の見通し力は必要)
私自身は、ご依頼者の「手間の削減」のためにご依頼いただいている業務は
今後は減ると考えており、今、受けている業務について
「人がやらないとダメな仕事なのか」の視点で
業務工数の見直し、圧縮を図っています。
その上で、お客様が自社でできる業務であれば、お客様のフィーの圧縮になります。
弊所はその分時間と手が空くので、我々でしかできない仕事に集中することができます。
結構なスピードで世の中が変わっていると感じており
このタイミングで次の一歩を踏み出したいと考えています。
(2025年03月発行)